新年度が始まったばかりの2025年4月。
本来なら新入社員が希望を胸に社会人生活をスタートさせる時期ですが、驚くべきニュースが飛び込んできました。
退職代行サービス「モームリ」によると、4月1日~7日の1週間で、新入社員からの退職依頼が93件にのぼったとのこと。
これは前年同期の約2.8倍という、異常とも言える数字です。
入社直後で退職を決める理由とは?
退職を希望した新入社員たちは、一体なにに耐えられなかったのでしょうか?
モームリが公表した主な理由は、以下の3つです。
労働条件の相違
「聞いていた話と違う」
――入社前の説明と、実際の働き方に大きなギャップがあるケースです。
・残業ほぼなしと聞いていたのに、初日から終電
・テレワークありと言われていたのに出社強制
・配属先や仕事内容が説明と大きく異なる
▶「騙された」と感じた時点で、信頼関係が崩れてしまうのです。
休日出勤の未説明
「休みの日も出てと言われた。そんな話、聞いてない…」
・面接では触れられなかった休日出勤を突然命じられる
・実際には“事実上の休日なし”の職場環境
▶こうした「情報不足」や「説明不足」は、信頼を大きく損ねます。
職場環境への不満
「上司が怖い」「空気がピリピリしてて息がつまる」などの“心理的ストレス”が大きな要因に。
・初日に怒鳴られた
・話しかけても無視される
・雰囲気が暗くて、居心地が悪い
▶特に新入社員は、“空気の悪さ”や“人間関係”に敏感です。
「この職場に長くいられない」と感じるまで、時間はかかりません。
退職代行サービス利用の背景
退職代行サービスの利用が増加している背景には、以下の要因が考えられます。
- 退職への心理的ハードルの低下:転職が一般的な選択肢となり、無理に長く勤める必要を感じない風潮が広がっています。
- 売り手市場の影響:大学生の就職内定率が過去最高を記録し、若手社員が他の企業への転職を容易に考えることができる状況です。
- 労働条件の不一致:入社前の説明と実際の労働条件にギャップがある場合、早期退職の要因となります。
| 退職急増の背景的要因 | 内容 |
|---|---|
| 売り手市場の継続 | 若者が「辞めても再就職できる」と思える環境 |
| 転職・副業の一般化 | 終身雇用にこだわらず、柔軟な働き方を選ぶ意識が定着 |
| 働くことへの価値観の変化 | 「苦しんでまで続ける意味はあるのか?」と考える世代の登場 |
| SNSでの情報共有 | 「辞めた人の声」が可視化され、退職の心理的ハードルが下がっている |
管理職の負担増加とその影響
新入社員が入社直後に辞めてしまうという現象は、単に「若者が辞めた」で終わる話ではありません。
その裏で、大きなプレッシャーと責任を背負っているのが“現場の管理職”です。
育成コストが水の泡に
新入社員が入社すれば、教育やOJT(On the Job Training)で時間も労力も使って指導します。
しかし、その社員が数日~数週間で辞めてしまえば…
・教えた内容が無駄になる
・教える側も「自分のやり方が悪かったのでは」と自責の念を抱く
・他の仕事との両立が難しくなり、業務負担が倍増
管理職にとっては、「教えてもすぐ辞めるなら、何のために時間を割いたのか」と感じざるを得ません。
業務のしわ寄せがチームに波及
新入社員が抜けると、単純に“人手が1人分減る”だけでは済みません。
・予定されていた業務分担が崩れる
・他のメンバーにしわ寄せが発生し、チーム全体の士気が低下
・管理職自身がプレイヤーとして現場に入ることも
本来マネジメントに集中すべき管理職が、現場対応+精神的ケア+引き継ぎ調整+報告対応と、1人で何役もこなす事態に陥ってしまいます。
管理職の「燃え尽きリスク」も上昇
こうした状況が続くと、管理職自身が限界を迎える可能性も出てきます。
・休職や転職を考える管理職も少なくありません
・「どうせすぐ辞める」「また1から育てるのか…」とモチベーションが低下
・上層部からは「なぜ定着しないのか」と責められ、板挟みに
企業の対策と取り組み
| 対策項目 | 具体的な取り組み内容 | 効果・目的 |
|---|---|---|
| メンター制度の導入 | 先輩社員が新入社員の相談相手となり、業務や人間関係の不安をサポート | 孤立感の解消、心理的安全性の向上 |
| 労働条件の明確化 | 実際の勤務時間や業務内容を入社前に詳細に説明。配属後のギャップを減らす | 入社後の不信感や「聞いてた話と違う」の防止 |
| 働きやすい環境の整備 | フレックス制度、在宅勤務、パワハラ対策、人間関係の見直しなどを継続的に改善 | 社員満足度の向上、定着率アップ |
メンター制度の導入
「わからないことを気軽に聞ける先輩がいる」――それだけで、新入社員の不安はぐっと減ります。
労働条件の明確化
「聞いていた話と違う…」をなくすために、入社前の情報提供は徹底すべきです。
働きやすい環境の整備
環境が合えば、人は続けられる。今の時代、仕事の“しんどさ”よりも“働きやすさ”が重要視されます。
まとめ
新入社員の早期退職が増える中、企業や管理職に求められるのは「厳しく育てる」よりも、「向き合って対話する力」です。
- 入社前の情報を誤魔化さない
- ギャップを感じさせないように丁寧に説明する
- 不安を打ち明けられるような空気を作る
📌 「信頼できる会社かどうか」が、初日から試されている――そんな時代になっています。
そしてその退職代行のニュースの裏で起きているのは、ただの“若手離職”ではありません。実は、“教える側である管理職の疲弊と孤立”が深刻な課題になっています。
「辞める新人」よりも「辞めそうな管理職」にも目を向けて
退職代行の裏で起きているのは、“教える側”の疲弊と孤立です。
新人の離職対策だけでなく、現場を支える中間管理職をどう守るかが、これからの組織運営のカギになるでしょう。
- 管理職に対するケアやフォロー体制を強化する
- チーム全体で新人教育を行い、負担を分散させる
- 「辞める理由」だけでなく「辞めさせない仕組み」を見直す
<参考ニュース>
・テレ朝news
・日本人材ニュースONLINE
・NLIリサーチ
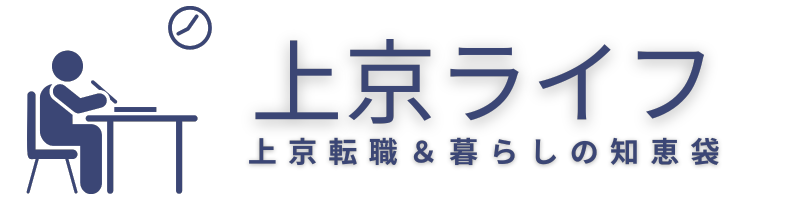
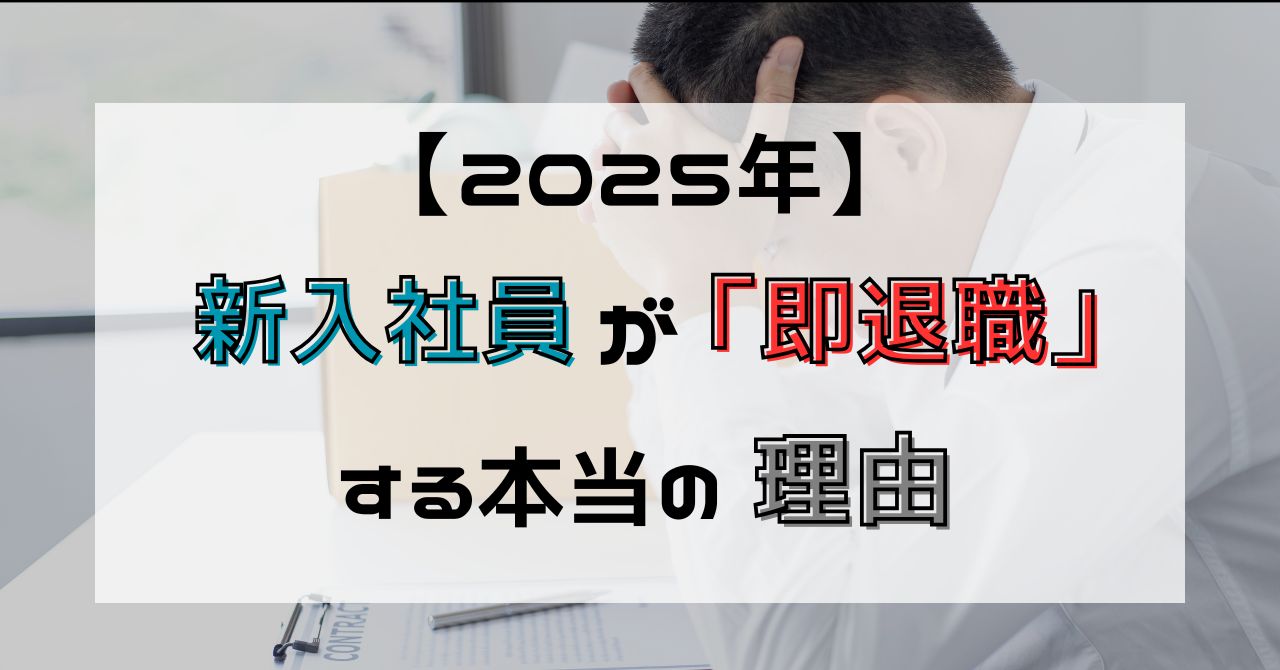
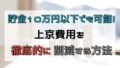
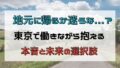
コメント