知らずにやってしまう前に知っておきたい基礎知識
まずトレスってなに?
イラストを描く人やSNSで作品を投稿する人のあいだで、最近話題になっているのが「AIトレス」という行為です。
トレス(トレース)とは、すでにある画像や写真の上から線をなぞって、自分のイラストとして描き起こすことを指します。
これは昔からある技法で、練習のために使われることも多く、まったく悪い行為というわけではありません。
トレスが使われる主なケース:
- 絵の練習として「写真や資料をなぞる」
- アニメや漫画の制作現場で、同じキャラを安定して描くために使う
- 自分の過去作品をなぞって修正・再描画する
大切なのは、「誰の絵をトレスしたか」を明記すること、そして目的をはっきりさせることです。
では「AIトレス」とは?
「AIトレス」とは、AIが自動で生成した画像をなぞって、自分の絵として仕上げる行為を指します。
一見すると、「AIが作った画像だから自由に使ってもいいのでは?」と思ってしまいがちですが、ここに落とし穴があります。
AIトレスの何が問題なの?
❶ 著作権の問題
AIが出力した画像は、「学習の元になった絵(=著作物)」に似てしまっていることがよくあります。
つまり、自分が知らないうちに、誰かの絵をそっくりなぞってしまっている可能性があるということです。
▶ その結果、「トレス元の作者から指摘されて炎上」というケースが増えています。
❷ 倫理的な問題
AIが出した絵をなぞったのに、それを自分が描いたかのように発表すると、
- 努力して描いた人を軽視している
- 「ズルをしている」と見られてしまう
- 見ている人をだましているように感じられる
などの理由で信頼を失うリスクがあります。信頼というものは築くのは大変ですが失うのは一瞬です。信頼を失えば仕事を失うも同義なのです。
トレスの正しい使い方とは?
トレス自体は「悪」ではありません。
以下のようにルールや目的を守って使えば、むしろ学びにつながる行為です。
| 使用目的 | OK / NG | 説明 |
|---|---|---|
| 絵の練習として写真をなぞる | ✅ OK | 個人の練習目的であれば問題なし。公開する場合は「練習です」と明記を。 |
| 自作の下書きを清書 | ✅ OK | 自分の絵をなぞるのは当然OK。 |
| 他人の絵を無断でトレスして発表 | ❌ NG | 著作権侵害の可能性あり。必ず許可を取ること。 |
| AI画像をトレスと明記して発表 | ⚠ グレー | 元画像が著作物に似ていると問題に。トレス元とAIの使用を明記するのが無難。 |
なぜバレるのか?|よくある5つの理由
素人目にはトレスを見抜くことは難しいです。しかし本物の絵師は些細な違和感から検証しトレスを見破ることができます。
以下の表に、AIトレスがバレてしまう主な理由をまとめました。
| バレる理由 |
|---|
| 線の一致(元画像との輪郭がピッタリ) |
| 構図・ポーズが同じ(左右反転などしても判別される) |
| 背景や装飾がそのままAI画像と一致 |
| 画像検索ツール(Google画像検索など)で元画像が見つかる |
| AI特有の不自然さ(指の本数・顔の歪み・装飾の破綻など)で違和感が出る |
AI画像は「見覚えのある構図」が多く、トレースした場合すぐに特定されやすいのが特徴です。
また、AI生成物には「独特の間違い」があるため、プロやファンの目にはすぐバレてしまいます。
なぜ炎上してしまうのか?
なぜトレスして炎上してしまうのか?原因は主に以下の5つです。
・無断トレス
・著作権侵害
・クレジット未記載
・AI絵を自作といい商用利用を続けている
・説明なし、不誠実な対応
無断トレス
最も多く炎上の原因になっているのがこれです。
他人が描いた絵や、AIで生成された画像を勝手にトレースして公開・発表してしまうという行為です。
なぜ問題なの?
- 本来、他人の作品を使うなら「許可」が必要です。
- トレースは“模倣”であるにもかかわらず、「自分で描いた」ように見せていると、盗作と受け取られます。
- 特にSNSでは「見覚えがある構図」「同じポーズ」などで、元絵がすぐ特定されやすく、発覚の可能性が非常に高いです。
著作権侵害
AIが学習して生成した画像であっても、元になっているデータが誰かの著作物である場合が多く、
それを無断でトレス・公開・販売することは、法律的な「著作権侵害」にあたる可能性があります。
よくある誤解
「AIが作ったんだから問題ないでしょ?」
実は、AIが生成した画像が元の著作物に“似すぎている”場合、トレスした人や公開した人が責任を問われる可能性があるとされています。
とくに企業やプロのクリエイターが関与している場合、訴訟に発展するケースもあります。
クレジット未記載
AIを使ったことや、元にした画像の出典を明記していないことも、炎上の大きな火種です。
なぜかというと…
- まるで「完全に自分で描いた作品」のように見える
- 見た人に「だまされた」と思わせてしまう
- AIを使って描くこと自体は悪くなくても、「隠すこと」が不誠実に見える
クレジットや出典を明記するだけで、トラブルの大半は防げるケースも多いのです。
AI絵を自作といい商用利用を続けている
AIで生成された画像や、それをトレスした絵を販売・宣伝などに使うときには特に注意が必要です。
こんなケースは要注意:
- トレスしたイラストをLINEスタンプやグッズにして販売
- 同人誌の表紙に使う
- イラスト販売サイトで販売する
こうした行為は「お金が関わる」ため、ファンや制作者の怒りが一気に爆発しやすく、炎上の確率が急上昇します。
説明なし・不誠実な対応
炎上したときに最も良くないのが、「黙り込む」ことや「ごまかす」ことです。
炎上が拡大する流れ
1. 指摘を受ける
2. 無視・削除・ブロックで対応
3. 認めない・謝らない・説明しないで火に油が注がれる
4. SNSでさらに拡散され、大炎上
炎上したときの正しい対応は、
すぐに投稿を取り下げる
トレス元があることを認めて謝罪する
可能ならば、元作者に連絡して許可を得る
といった、誠実な姿勢です。
AIトレスをめぐる世間の目
- 「努力せずにズルをしている」
- 「他人の作品を利用してるのに、あたかも自分が描いたように見せている」
- 「AIを使うのはいいが、トレスして稼ぐのはダメ」
こういった声がSNSでは広がっています。
技術ではなく“誠実さ”が問われる時代ともいえます。
結論|AIの活用にはルールと誠実さを
| やっていいこと | 避けるべきこと |
|---|---|
| AIを参考に構図や発想を得る | AI画像をなぞって完成品にする(とくに無断使用) |
| AI生成と明記する | クレジットや説明を省略して発表する |
| 非商用で実験的に使う | 商用利用・販売に使う |
AIは便利なツールです。しかし、「他人の権利や感情を踏みにじらない」という当たり前の配慮を忘れてはいけません。
“バレなければいい”ではなく、“堂々と使える方法を選ぶ”ことが、創作者としての信頼につながります。
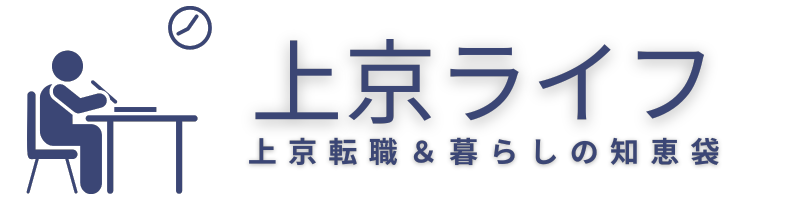
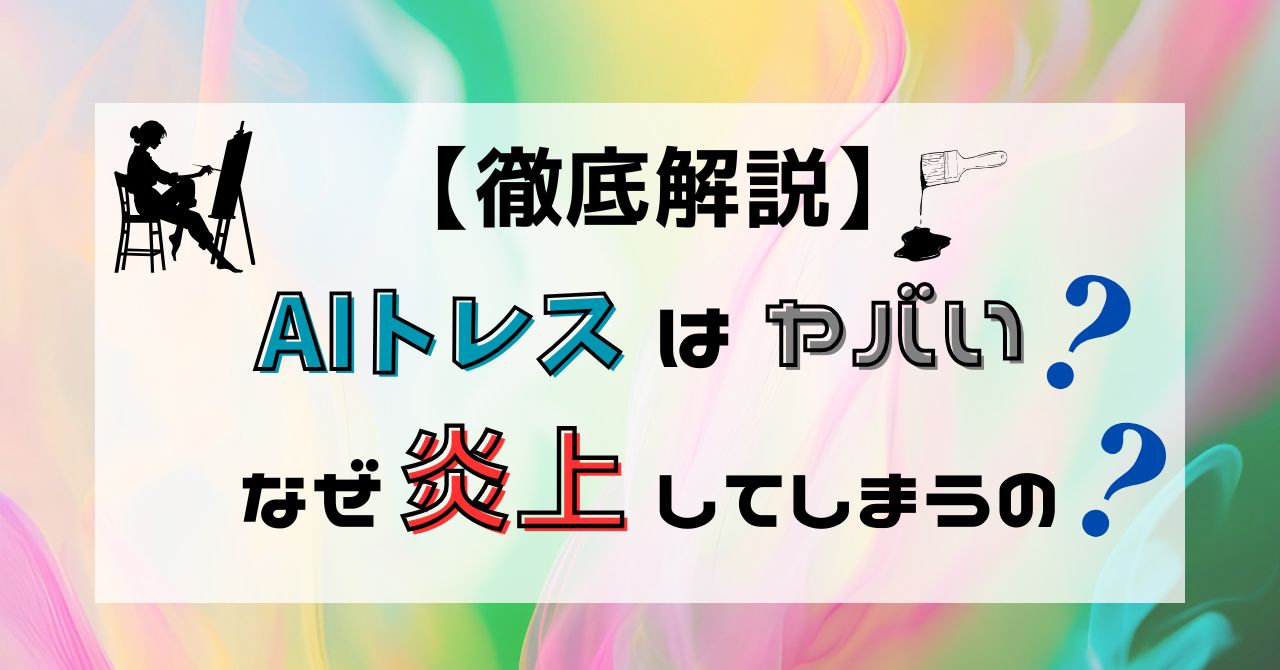
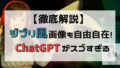
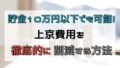
コメント